 連載記事
連載記事2020/02/08
 連載小説・デッサン いろはにほへど
(3)陸援隊
連載小説・デッサン いろはにほへど
(3)陸援隊
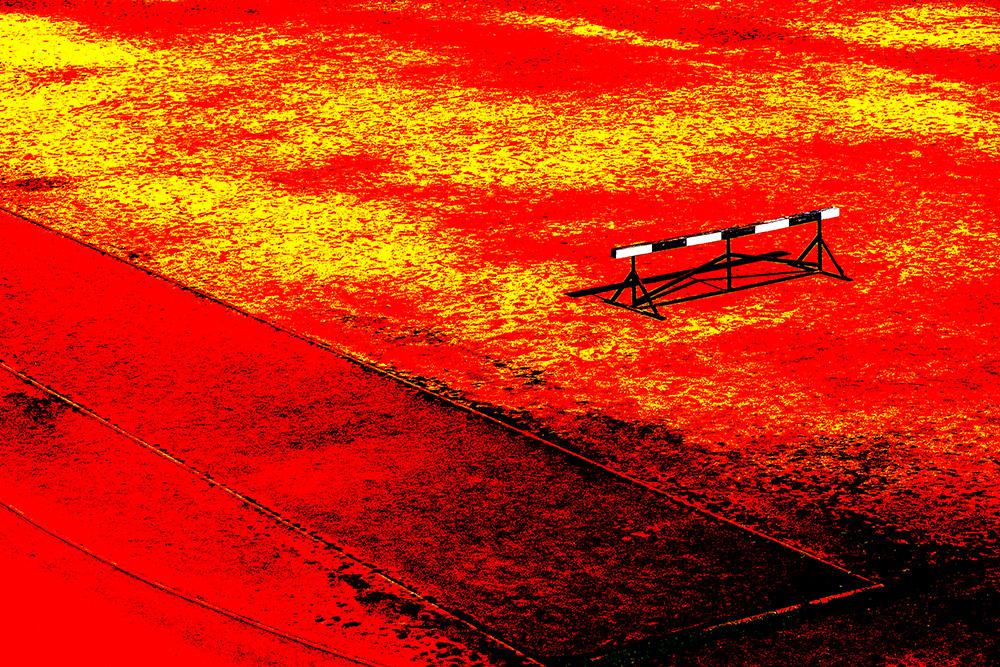

「中村さん、」
と扉が開いた。
辛島 寛
槙野茂樹
であった。
「例の件どうでした、」
とは団体結成時における顧問の先生の依頼の件ということであり、当校はクラブ結成時顧問一名を必要とし、書面に記さなければならず、その適当な人物がいたかどうかを聞いているのである。
何しろ入学式の翌々日のことであるだけに内情が分からない。クラス分けが終わり、ガイダンスを聞いたのがこの日であるのだが、
「これを学生課だったか教務だったかに持ってゆけ、」
と、史邦は言った。
「だれですかこの人は、」
「よう分からん、分からんがなってもろうた、」
「そんな馬鹿な、」
「歴史学を教えるとか言われていたから、歴史学の先生だろう、」
文学である。
文学畑出身の東田先生はどういう理由でか、その時期当大学においては、歴史学と外書講読の講座を開講されていた。
入学式半ばにして史邦と辛島が外に出、クラブ勧誘に取り巻かれたことは先に述べた。その後、辛島が史邦との話の中で、実は高校時代を通じて陸上競技をやっていたのだと問われるままに答えている。
「ほうか、陸上をねえ、」
別に感心している訳ではない。
「むしろ、茶よりはむいているかもしれん、」
その程度にしか思っていない。
その陸上の中の何なんだと聞くと、ハンマー投げだと答えた。そうかとはいってはみたものの、実際史邦はそれからかなりの時期、丁度現物を目の当たりにするまでの間、砲丸投げと混同していたのである。
ハンマー投げは、今でこそ七・二五kgの鉄球にピアノ線というスマートな競技になってはいるが、元来はまともにハンマーを振り回す競技であったらしい。らしいというのは辛島の口述を鵜呑みにしている訳でその歴史の実態は定かではないのであるが、いずれ調べてみる事にしよう。
「面接の時に君は何かクラブに入っていましたか、と聞かれたので答えると、それはそれはと面接官が言うものだからこの際売り込んでやれと大風呂敷を広げてやったんです。そうしたら何と言ったと思いますか、勝手にやってくれと言われました、」
勝手にやってくれと、その時の面接官は言った。要するに、君がどれほどの者かはさておいて、まあ、せいぜいがんばってくれろという意味であろう。
辛島は、茶道部勧誘員の新入部員名簿に名前を記入したので、後日クラブ室まで来るようにと声がかかり、一応は例をとり形式上済ませてきた。その体格のせいで他のクラブからも二三声がかかっていた様だが、いずれも応じてはいない。
槙野茂樹は、彼も又寮生である。辛島といつの頃からか、割りと早い時期に一緒に歩いていた。
その二人が、心機一転何かをやろうと選んだのがやはり陸上競技であった。
が、その陸上部が存在しない。
いや、過去にはあったらしいが途絶えてしまっているらしく、それでも部室ぐらいはあるのではないかと、幻の部屋を探して歩いたが、部自体かけらもないのであるから、これまたあろう筈もない。
寮の史邦の部屋で今日はああだったこうだったと夜毎話をする。
「いっそのこと、お前達がつくれば良かろう、」
と、事相成った次第である。
槙野茂樹について、もう少し触れておこう。
槙野は広島呉の人間である。自衛隊呉潜水艦基地の手前、かつて、旧海軍の誇る戦艦大和を造ったドックが見降ろせる位置に居を構える槙野某氏の二児の長男に生まれる。
父、槙野某氏はいつの頃からか、心臓を病んではいたが、近郊の日新製鋼株式会社の教育指導課に勤務しており、当時心臓の状態は決して好い方ではなく、悲しい話もむしろ意外ではない様であった。
槙野は非常にナイーブな性格であったが、時として彼にはその性格を反対に押し出すことによって自分を確立させるという一面が見受けられた。そのことが、彼に好意を寄せる人間にとっては魅力となるのではあるが、好意を持ち合わせていない人間には苦痛に感じられるようでもあった。しかし、そういう場合はまれであり、ほとんど、融通のきく者にしかその一面は見せない。
呉港高等学校在学中を通じて陸上部に籍を置き、短距離を専門に活躍していたのである。
その辛島と槙野の二人が心機一転何かをやろうと選んだのが、やはり陸上競技であったことは能がないと云えば能がないのではあるが、この陸上競技を選んだのには多分に史邦の意思がはいっていたのかもしれない。
「これを学生課だったか事務だったかに持ってゆけ、」
そうすることで辛島と槙野は陸上部員になれる。
史邦はその経歴故に、このこじんまりとした大学では好意の目で見られることがままあった。
「徳永さんーーー、」
と、学生課窓口に寄り掛かる史邦は、当大学のOBでもあり職員でもある内側の人間の者の仕事の手をとめ、話に夢中である。
「何で俺の名前を知っている、」
何でと言われて多少驚いた。彼はガイダンスの際、その注意事項をあらかじめ学生に伝える中で、俺は徳永だ、俺は徳永だ、と言っていたのである。
「そうだったか、そりゃあいい、」
とは、徳永氏。
「徳永さん、そこの鍵をかしてもらえんですかね、」
「どの鍵だ、」
「ほれ、そこの、それ、」
「これか、」
「それ、それそれ、」
その日以来、陸上部はクラブ棟二階のミーティングルームIIの部屋を使い始めた。当初、
「なにをたくらんでいる、」
と、徳永から言われ、
「良からぬ相談をするため、」
と答えた史邦であった。クラブ棟二階のその部屋を使うためには、表向きは設備使用許可願いを毎日提出して鍵を借り、その日の内に鍵を返却しなければならず、結構手間のかかるものであった。何度目かのある日史邦は辛島に合鍵を造らした。
「毎日四時半に鍵を借りて六時にかえす、これでゆこう。」
造った合鍵はもちろんのこと、主に使用はする。学生課にある鍵は形式上借りる。その鍵は、いわば陸上部の宣伝に使用するというものである。
毎日々々、四時半になると学生課に史邦が現れることになるのである。そして、これまた日々、六時半を時計の針が回ると学生課には史邦の姿がある。
実のところ、徳永にとってはたいそう迷惑な話である。五時が来ればその日の仕事は一応終わりを告げる。又、毎日ではないにせよ、時間外の仕事もある日もあるだろうが、とにかく、陸上部の連中の練習が終わらない内は、帰りたくても帰ることが出来ない状態になりゆきじょうなってしまったのである。
実質的には、鍵を借りたその日からミーティングルームIIは陸上部部室と化けてしまった。
【新たなるサークル等団体は、その初年度をもって同好会とし、後に各サークル等の承認を受け、部に昇格するものとする】
という内容に付属して、部に昇格しなければ部室はもらうことができない仕組みになっている。そういう仕組みになっているけれども、実のところクラブ棟は既に手一杯の状態であり、部であろうが同好会であろうが詰まるところ関係ないのである。
と、なれば、既成事実を造りあげてしまう手段を採った方が早道であろう。
入学式の翌々日に顧問を得、その次の日に団体結成届を提出し、更に数日を開けて部室を得た。辛島と槙野の活躍する場所の一応のものはこれで整った。後は、両人の器量次第である。
「まあ、しっかりやれ、」
「やりましょう、」
「とは、」
史邦が意外だったのは両人の表情であった。既に史邦を頼り切っている。
「冗談じゃあないぜ、お前さんらの活躍する場は既にまにあっている、あとはしらんぜ、」
「そんなぁ、」
気が抜けたような顔をしている。
笑いだした。
笑いだしたのは史邦である。
「面白いのお、」
「面白くぁ、ありません。何が面白いもんですか、」
「お前たちの頭の中がよ、」
辛島と槙野の頭の中には広く史邦の座る場所が開けられている。その場所に史邦が座ってくれなければ、両人の構想そのものが空しく掻き消えてしまうのである。みじんもなくなる。いまさらの変更が不可能な程に広く、その場所はとられてしまっている。
彼らが大学側に提出しに行った書類には、上の寮からの同志の名前と史邦の名前が新たに書き加えられていた。史邦の名は、学生責任者と部長の桁に書き込まれた。
顧問の東田先生は史邦に、
「俺はなんもせんぞ、」
と、言われた。
「陸上のことは何も分からぬ、勝手にやれば好い、」
とも言われ、
「それで結構です、」
と言った史邦であった。
その時の東田先生と同じことを、今度は史邦が両人に言わなければならぬ立場に立ってしまった。
だから、
「面白いのお、」
である。
史邦は、陸上競技に付いての知識は皆無であった。
高校時分に籍を置いたヨット部も、一緒に入った友人と、夏場を過ぎて何だか馬鹿らしくなってやめてしまった。馬鹿らしくなったのはヨットではなくて、人間関係である。友人と先輩の人間関係を見ているうちに何だか馬鹿らしくなった。
あの先輩がいるから一緒に入部しようと言った友人だが、その友人がやめようと言いだしたものだからやめたまでのことである。初めから大した心づもりもなかったから、あっさりと史邦は退部している。
他には、小説同好会を自分達でつくっているが、何をしていたかと言えば金集めの方が主になってしまっていて小説同好会といえるかどうか疑わしいものである。
この小説同好会に関しては数々の話しが存在しており、幼い日々の史邦の行動が面白いのであるけれども、この物語の本質とは直接的なつながりを持たないので、ここでは触れない。
習いごとは、ギター、ダブルペース、書道、剣道、柔道と数あるが、どれもまるでものになっていない。しいていえば剣道ぐらいのものであろう、当時、初段までとってやめている。
この剣道については、史邦の名誉の為にことわっておくと、やめたのではなくて、やめざるを得なかったのである。史邦の意思ではない。先生が居なくなったのである。
しかしながら、陸上競技に知識がないからといって、そのことが即ち不可能を意味するものでは決してない。初めから経験者である者はいない。
当の史邦は、そんなんことは根っから気にはとめていないらしい。
成り行き上、陸上部の元締めになってしまったことは事実である。
学生責任者、部長、主務 中村史邦
主将 辛島 寛
副将 槙野茂樹
副将 黒沢 某
幸 剛司
内藤 某
宮迫一郎
田尾広幸
二村 某
徳永一郎
総勢十名、全て一回生である。
二つある大学の寮の登りきったところにあるのが萌友、下に位置している、史邦の入っている寮が恒友、それぞれ名がつけられており、部員の全てがこのどちらかで寝起きしていた。
十名ともに寮生であった。
ある日、門出の祝杯をあげようということになった。
「中村さん、行きましょう、」
ドアが開いて顔がある。
新下関駅南口に四、五軒の宮が並ぶ一番手前の店、焼き鳥屋味善がその記念すべき場所となった。そこへ、ゆきましょうと顔だけ突っ込んで辛島が言っている。
玄関で上の寮の部員が待っていた。
「飲み会かね、」
と、言ったのは寮監で、いつになく親しく、
「いってきなさい、」
を、二度三度繰り返す。
玄関の、寮監が先程扉を開けて出てきたところに電話が置かれている。
「今日は祝杯をあげてきます、遅くなりますから先に寝ていて下さい、どこからでも勝手に入りますから、」
と、辛島。
通常門限は十時である。
「裏の鍵を開けておくから、そこから入りなさい、」
赤い電話が鳴った。
「中村さんにですよ、」
「先に行ってろ、追いかける、」
電話は大阪からの長距離であった。
中村の八幡太郎の叔母、千枝である。
家を出るときに、何かを感じていた史邦であったが、その何かが今姿を持って目の前にぶら下がった。
電話の内容がそれである。
(俺が馬鹿だった)
父、一男がだまされた。
相手はこともあろうに母の実弟であった。
史邦にとって叔父であるその男は、彼の事業の為に一男から都合五千万の裏書を受けていたが、事かんばしくなく行き詰まり、最後の額一千万を、いわば逃走資金にあて姿をくらましたという電話の内容である。
電話は言う。
裏書の抵当に入れた家がなくなるとのこと、尚、直接一男から聞いた話ではないので、どこまで話しが進んでいるかは不明だけれども、とにかく、帰って真相を確認しておいた方が良かろう、と。
思えば、史邦が下関へ来る前からそれらしい様子はあったような気がする。
叔父沖郎が幾度となく家に足を運び、金額がいくらだの、どこの銀行だのという会話を耳にしたことがある。しかし、まさか叔父が父一男をだまし、一千万を逃走資金に、姿をくらますなどとは考えもおよばぬことであった。
更に、
これを書けば物語が複雑になるであろうが、余談ながら書き加えておこう。
更に、沖郎が一男から金を引き出させて逃げたのには中塚実男存在が多分にあった。
中塚実男が今回の話しの結果の黒幕的存在である。
この、中塚実男は史邦の母方の親戚筋にあたる。
史邦の母佳子は四人兄弟の三番目に生まれた。
長男 風間 博
長女 令子
次女 佳子
次男 沖郎
この内、史邦の母佳子の姉にあたる令子が嫁いだのが、中塚実男である。
実男は風間家では評判が悪く、良く言う者がほとんどいなかった。
令子を嫁にした当時彼は警察に勤務しており、拳銃で令子をおどして今があるんだと、かつて史邦は風間の人間に聞かされたことがある。しかし、その話の真相は定かでないにしろ一騒動あったことは察しがつく。
警察を退き、岡山県の児島で被服工場を持ち、かなり悪どい商売をしている。彼にだまされ、泣かされた関連業者もずいぶんといたに違いないが、これは想像の域を出ない。
その被服会社も、終戦から一時期迄の、とにかく作れば売れる時代を経て、経済界の活性化に遭遇し、連鎖倒産という事態に至った。そういう事態を実男は巧みに読み取っていた。いわば、実男の頭の中では計画的な倒産であった。計画的な倒産である以上、次に興す事業の為の資金は当然のことながら準備されていた。その準備された資金をもとにラーメン屋へと、被服会社からはほとんど畑違いの分野へ転身を図った。
そのラーメン屋も『札幌ラーメン』と称し、次々と岡山市内はもとより更にその周辺へと拡大してゆく。昭和四十年代の後半である。
小知恵は働く。損得勘定は、その体質として人一倍敏感なものを持っている。
一時期は好機をもたらしてた『札幌ラーメン』拡張経営も、やがては頭打ちの状態に陥り、果てはどうにかこうにか、各店舗の切り売りにより生計を立てる様になってゆく。
目先の効くこの男も、青年期から壮年期にかけての意気盛んな頃を過ぎれば、もはや転身の為の殻を脱げなくなってゆくものであろうか。
どうでも好いことだ。
筆者は、史邦の視点からこの男を見た。この男の野望なり人となりは見る視点が違えばどういう風体を表すのかはこの物語においては何ら価値を持たない。あくまで、筆者はこの物語の主人公の史邦の目を借りていたまでのことで、より史邦に近い立場を採らざるを得ないのであるがこの際、それはどうでも好い事柄なのである。
中塚実男と玲子の間に雅之が生まれた。
自然、史邦とはいとこになる。この両人が住宅設備会社の経営をはじめた。シンセイ住宅設備というのが新会社の名称であった。
この会社が空中分解したことは先に述べた。空中分解する前の段階に実男がこのシンセイ住宅設備に乗り出してきている。それを機に一時は営業十名、下請け工事人二十余名いた人員が日々一人辞め二人辞め散っていってしまった。仕事をとってくる営業マンが順次辞めていったことは、ごくあたりまえの現象として、それはそのまま下請け工事人、とりわけ親方連中の頭痛の種となってゆく。死活問題として彼らのうえにのしかかってゆくのであった。
雅之は事務所にいて営業マンからの連絡を待つ。
史邦は才があるのか、雅之と一緒に営業活動をしていた時期に雅之をしのぐ成績をあげていた。
雅之の方が三つ史邦よりも年上であり、兄貴分であったことと、右の事情により事務所内の勤務についていた。
史邦は、当時新会社ができて間もない為に経費の軽減の意味で外勤につく。しかもその処遇は全て他の外勤者と同等のものとし、彼の給料は完全なる契約者との歩合によって成り立つ形式をとることを自らの意思により決定している。
シンセイ住宅設備の業績は日々伸びてゆき、設立後半年でその業界の中堅的存在になっていた。
実男は、ぬかりはない。
両名の新会社の事務所と倉庫の場所に自分所有の建物をあてがい、史邦が後日知ったことには、月々の家賃をとっていたる。
とりわけ、事務所と倉庫の家賃を自分の息子と甥のやる会社からとることは問題ではない。むしろ、大人としては至極当たり前の事柄である。
彼のぬかりなさはここではない。
この両名を自分の手の届く範囲の内に置き、どうやらやれると踏んだ瞬間に、さっと身を乗り出してくる点にある。
雅之にしろ史邦にしろ子供である。当時雅之二十四歳、史邦二十一歳である。しかも、実の父であり叔父にあたる人物で実男があっただけに事は尚更である。まんまと乗せられてしまった。
当初の半年間、その会社は合法的な存在ではなく、いわゆる幽霊会社であった。当時、有限なり株式の形態を採っていなかったのは多分に本人たちでさえこの会社がうまくゆくものであるかどうか疑わしく、成行きをしばしの間見ていようというつもりであったらしい。やがて、これはゆけるのではないかと両名が考え出した頃合いを見計らっての実男の出番となったのである。
「今日からこの会社は全て私がめんどうをみる、」
と、ある朝、事務所で朝会を開いていた時に皆を前にして実男が語った。
驚いたのは他の従業員達であった。日ごろからあの人、つまり、実男がこう出るであろう予感をすでに皆は雰囲気として持っていた。その雰囲気も決して好意的なものではなく、むしろその逆である。
その日より後、
「中村君、今日ちょっと時間をとってもらえるかね、」
と、従業員の一人、三十三歳になる河内が言う。
不思議なことに、二十四、二十一という殆ど子供のような二人に、好い大人が従業員としてついて来てくれるのである。
社内ばかりか対外的にも彼らのまわりにはそういう親身になってくれる人間が多かったことは、不思議といえばこれほど不思議なことはない。
史邦達の仕事が外勤であるだけにその気になれば時間はいくらでもさけた。
仕事から離れていきつけの喫茶店へ入ると、そこにはほぼ全員の社員の顔が揃っていた。
「実は、例の件だがーーー、」
と、河内は切り出した。
誰と誰はもはや会社を辞めることを決心していて、誰と誰はすでに次の仕事の目鼻はつけている。又、誰と誰は同業種、いわばライバル会社から声がかかっているがまだ迷っていると、皆のおかれた各々の立場を説明した。
「私たちはできることならば君の会社を辞めたくはないということは分かってほしい。しかし、現状ではそれは望めそうもなく、又、同じにそれぞれに生活があることも理解してくれると思う、」
(わかる)
分かるだけに史邦は奔走していた。
従業員の気持ちを完全に無視し、自分の利だけを追求し始めた実男ともなんどもぶつかった。
河内は続ける。
「君が独立してくれさえすれば、皆は君に賭けるつもりでいる、どうかね、もう一度皆とやってみてはくれないだろうか、斉藤も同意だ、」
斉藤とは下請け工事の親方である。
「一緒にやろう、」
と言ったのは藤原。
(そうできれば、どれほどすくわれるか)
そう思った。が、話の結果。
皆の気持ちは非常なものとして受けるが、自分は雅之とはいとこ関係にあり、あれでも実男は自分の親族であるから、そういうことは不可能だというところに落ち着いた。
「声をかけられる状態になればいつでも声をかけてくれ、一緒に仕事をしような、」
と言う。
(俺はちがう、皆とはちがうんだ)
それから、河内は他の人間の転職の世話の面倒をみ、自らは残った。
一時の社員は既に影だけを残して去り、後に残されたのは河内と史邦の二人であった。
こうなってしまっては仕事どころではない。しかし、
「お前もいかんか、」
と、雅之を事務所から追いたてるけんまくであった。
雅之はしぶしぶと出てゆく。
父親に叱られた子供である。ある意味で、この時点での実男の姿勢はごく当たり前の所作であったかもしれない。又、他の社員はともかくも、史邦はまだ子供であり経営者ではなかったともいえるであろう。
しかし、筆者は史邦の子供さ加減を計りに載せてはかろうとするものではない。人間、あるいはその人間の情という次元おいて何が他よりも優先するかという事情をはかりたかったのかもしれない。この点、筆者は史邦と共通する部分を有しているかもしれないが、まあいい。余計なことだ。
そういう訳で、もはや企業の体をなさなくなったシンセイ住宅設備に史邦は残っていた。
そういう史邦であったが、その彼が、
(やめた)
と、決心した出来事がおこった。
雅之の行動が、あるいは彼の感覚が起爆剤となったのである。
実男と同種のものを雅之に見たのである。
その時期、史邦の家では改築を行っていた。それに関して、改築する金があるのならばなぜこの会社にその金を回そうとしないのかと雅之は史邦に行った。
(何のことだ、何うしたというんだ)
「金持ちの親戚を持ちたいとは思わんか、」
「何を言ってる、」
「そういう親戚がおれば手形もきらんで済むということだ、」
「馬鹿なことを言うな、何を気弱になっている、」
(やめたやめた馬鹿々々しい、この男もおやじと同類かえ)
その夜、親方が史邦を訪ねてきた。
この親方はシンセイ住宅設備の仕事一本やりであったため、多大なる迷惑を及ぼしていると史邦は感じていた。
「親方すまんことをしたのぉ、」
「いやいや、お互い様よ、」
「こうなるとは思わんかった、」
「そりゃあそうだ、こうなると分かってりゃあお互い苦労はしやしねえ、」
「ほんとうだ、」
あっけらかんとしたものである。親方にしてみれば死活問題であるべき筈の事態を笑っている。このあたり、さすがに歳を経ただけあり、史邦はこの男に余裕すら感じるのである。
「そりゃあそうと、いろんなことが近頃耳に入ってくるんでね、あんたにも是非聞いてもらっておこうと思ってやってきた、」
「吉報ならいいがね、大歓迎だ、」
「なにを呑気にかまえていなさる、社長のことさ、」
「どこの社長だ、」
「そりゃあない、」
「こりゃあいい、」
二人。笑った。
「いや冗談はさておくとして、中塚のことだよ、」
「そうか、ナカツカか、」
「あんた、月給何ヶ月待ったんだね、」
「そんなこともあったの、たびたびさ、」
「どういう理由で、」
「苦しかったんだろう、支払いとかに、まあそんなとこさ、それがどうかしたかね、」
「呑気だねえあんた、あんたの給料だろう、」
「気は長いが、呑気ではない、」
威張っている。
「間がぬけてるね、」
「そうかもしれぬ、」
と、真顔で答える。
「その間、つまりあんたに給料を払わなんだその時ということだが、アレは給料をとっていたかね、」
「知らぬ、」
「こりゃあたまげた、」
「いや、むしろ馬鹿げている、」
「いやいや、あんた冗談ではないぜ、」
「冗談はいっていない、」
親方は真剣な表情になり、続ける、
「アレはね、アレは給料をとっていた、いや、そればかりか毎晩、毎晩ですぜ、」
「毎晩どうしたというのだ、女でも買ったか、」
「馬鹿な、しかし似たようなもんでさ、日に十万から二十万バクチをしていたらしいんでさ、なに、ウチのがたまたま居合わせていたらしいんだが、そいつが聞くところによると、その日だけじゃあなく殆ど毎日顔を出してやがったんだと、ふざけてるねえ、腹がたたねえかい、アレにさ、」
「で、バクチは勝ったかい、」
「冗談はよしにしようぜ、俺ゃああんたのことが気がかりでさ、」
「そりゃあさかさまだよ、」
逆さまなのは自分こそ親方に迷惑をかけているということであり、尚且つその親方に自分が思われていることが、史邦にはこの上もなく嬉しいことだったのである。
史邦は何だかむやみに淋しい気持ちになった。
その気分が親方に伝わる。
「親方、助かったよ、」
「そうか、そりゃあ来て良かった、」
史邦は、一人で思っている。
やがて、
(潰そう、潰してしまわねば解決はつかぬ)
そう一人胸でつぶやいた。
誰もいなくなった事務所に車が二台とまっている。河内はまだ帰ってはいない。
(両方揃っている、今だ)
河内に聞かせなくても好い話しだ、
(河内さんには悪いが、これからこの会社を潰しにかかる。気に入らんかもしれんが代わりとなるものは用意してあるから、そこでがまんしてもらうことにする)
国道沿いの事務所の前には広く駐車場が設けられてある。
史邦は車を乗り入れ、歩き出す。
アルミのドアを開くと、果たして二人が首をそろえて内側にいた。
「早かったな、」
「やめた、」
「不調だな、」
営業成績のことを言っている。
「やかましいわ、馬鹿野郎、」
「———、」
奥のソファーに後頭を見せて実男は新聞に目を通とおしていた。が、その日頃ない史邦の期につと、向きなおった。
「てめぇら、ようも人をコケにしてくれるじゃあねぇか、」
「なんだ、何ごとだ、」
「いやさ、間違うんじゃあねぇ、俺のこたぁいざしらず、人のえゝ真人間を、てめぇらなんじゃとおもぉとるんじゃ、丁度、えゝ、てめぇらふてぇり、こけぇ座りゃがれ、」
史邦は既に実男の正面にいる。実男の向かいの椅子に片膝をかけて、まるで任侠映画の場面よろしく芝居がかっているが、本人はこれでその気はまるでなく、人の好い親方だの他の連中の顔だけが胸中にあった。
雅之は史邦の気に呑まれ、吸い寄せられるようにうごいている。
やがて、実男の座る長椅子に並ぶように座った。
その二人の顔を見るにつけ、史邦は爆発した。自分にこういう一面があろうとは、当の史邦でさえ目を見張る思いで頭のどこかに記憶していた。
史邦があらかた胸にためていたものを吐き捨てる様に放出した頃になると、さすがに実男は気を取り戻していた。
史邦の言葉の頃合いを見て実男が口を開いた。
「もうえゝ、よう分かった、」
全てを吐き出した史邦は息をついている。
と、何を思ったか、史邦にとって意外なことが目の前でおこった。
実男が息子雅之に対して爆発したのである。
唖然としているのは史邦である。予想も何も外のことであった。実際目の前の光景は信じられるものではなかった。
元の位置に、しかし、既に史邦の気に押されていた実男とは違う男が座った。
「おめぇ、よう言うた、今何を言うたか忘れるんじゃあねえぞ、二十歳そこそこのガキが五十面をさげた者に、おめぇが言うた、そのことだけゃ絶対に忘れるんじゃあねえ、」
そして、やゝ気を落ちつけ、
「おめぇにゃあ、そういう素質がある、」
(怒らせたかヘタぁ運んだのぉ、どねゃでもなれ後にひけるかい)
そうは思いながらも、又、
(ヲエン普通に戻る)
要するに史邦の興奮状態が徐々におさまりかけているということであり、まだその気を借りていなければ五十面の男の気迫に押されてしまいそうで、だから、まだ普通の状態に戻るべきではないと感じている。
それから何やら喋っていたが、実男の言葉の数程は史邦の頭の中には入って来なかった。
最後の言葉として、
「おめぇだけゃあ絶対に許さん、」
と、言っていた。
ヤクザを使ってでもウチの役員を何うしてくれると、将来史邦の就職先へ使いを出すとも言った。
後日、実男はシンセイ住宅設備より同種の会社へ移った者一人いくらという勘定で、その就職先の会社から金を巻きあげている。
そのシンセイ住宅設備の、いわばライバル会社も金を支払うことで現実問題の問題処理を済ませた。
(あの野郎、どこまで骨の腐った男だ)
と、史邦は親方からの話しに思ったのであった。
後の史邦は親方に協力して、親方のもとで営業部をおこしている。しかし、史邦はそこにとどまるつもりではなく、職人を抱えるだけ抱えて死活問題とまでなっていた親方への恩を返す為であった。
連載小説「デッサン いろはにほへど」をまとめて読む
(1)門出の花
(2)馬関へ
(3)陸援隊
(4)桜の木
(5)憂
(6)惨風
(7)思案
(8)思案その二
(9)物情騒然
(10)刺客
あとがき

準備中