 連載記事
連載記事2020/04/15
 連載小説・デッサン いろはにほへど
(5)憂
連載小説・デッサン いろはにほへど
(5)憂
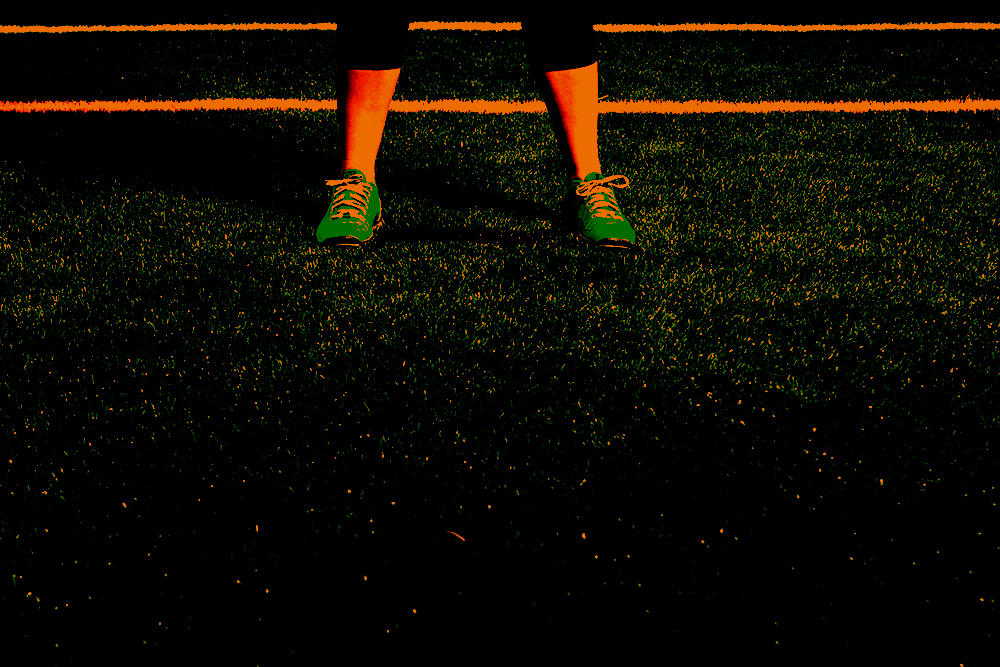

大学での史邦の生活は多忙を極めていた。
誰もやらない学祭の実行委員会の尻ぬぐいと、ひょんなことから陸上部の面倒を引き受けてしまったことで殆ど一日を潰していた。
大学祭の実行委員会を考えてみてくれろと学生課の徳永より話があった時は、一度は断ったのであるが、史邦と同じ寮に住む冨永が別の形で、やはり大学祭の件を持ち込んできたのである。
学生部の原田先生から冨永に委員長を引き受けてくれろとの話しがあった。冨永はソフトボール部の部長をしており、原田先生はもとより体育実技を教え、体育系である冨永の部もあさからず関係があった。そこで、引き受けてしまいたくないが、一応考えさせてくれと事相成った次第であった。
「お兄さん、」
と、史邦のことをそう呼ぶ。
そう呼びはじめたのは磯元が最初であった。
余談だが、
二十五歳の新入生が寮に入ってくるらしいが、どんな二十五か試してやろうと、この蛮カラは思った。
この寮では寮長以下必要と認められる役を学生の自治に任せていた。寮監が二十五の新入生が入寮することを事前に彼らに告げていたのである。
辛島に年がばれていなくとも、いずれは周知の事実になる事柄だったことを思うと、史邦の気配りも結果的には無用の長物であった訳である。
磯元は果たしてこれではないかと思うめぼしい奴とすれちがった。
どことなく違うには違うが、二十五にはとうてい見えない。
(いや、しかしこいつだろう)
史邦の第一印象である。
「君か、二十五で入って来たというのは、」
二十五の奴と、まるで囚人番号で呼ばれた風であった。
史邦はぷすっとしている。
(やはり、こいつか)
「ちょっと、部屋まで来んかね、」
「———」
あさっての方向を向いている。
(こいつ)
と、そう磯元が思った瞬間、二十五は喋った。
「暇じゃけぇ行こうか、茶でも出るんかの、」
二十五だとしても下級生である。下級生が上級生に向かって言う言葉ではないのだが。
「どうしたんかの、」
磯元は窮していた自分にあわてた。我をとりもどし、
「出す、」
茶を、である。
「ゆこう、ゆこう、」
と、言って歩き出したのは史邦の方であった。
気を呑まれて、つい歩を進めた磯元であったが、彼の部屋の方ではない。
(わしとしたことが)
苦笑い。
「お兄さん、そっちじゃあない、」
と腕をとった。
「磯元さんの部屋はどこじゃったかの、まだ馴れてないけぇ、」
(こ、こいつ、知ってのことか)
それ以来、史邦はオニイサンと呼ばれるようになった。
それから、磯元が史邦に対してどう評価を下したのかはここではいいことだ。
史邦はことの他この種の力関係を嫌った。いわゆる、立場上だけでの上下の力関係をである。ただ単に力関係を否定したというのではなくて信頼関係を伴うものであれば、それはそれで認めた。
この時もそうであった。
史邦の挑発にのれば、それはそれで大した奴ではない。
史邦もそう踏んだ。
磯元こそいい面の皮であった。よし、試してやろうと思っていたのがその相手によって自分が試されたのである。
以来、磯元に敬服している冨永と供に、史邦はオニイサンと呼ばれた。
そう呼ばれることに喜び等は毛程も覚えなかった史邦ではあるが、まあ、いいだろう位に思っていたのもつかの間、彼ら二人は場所を構わない。大学の敷地の、殆どはしとはしとで、大声でよばわる。これには、大そう閉口していたようであった。
余談だが、またまた続いてしまったようだ。
冨永が史邦の部屋に先程から来て座っている。
「どねぇしたもんじゃろうかの、」
そういう意味のことを薩摩言葉で言ったのを史邦はこう理解した。
(よほど、やり手がおらぬようじゃな、)
「おらんのじゃ、誰もおらんのじゃ、皆そっぽをむいちょる、」
「しかし、まあ、やらぬ訳にゃあゆくまい、」
「やらぬわけにゃあゆかんでの、」
「ならば、やれ、」
「おいがか、」
「お前がじゃ、」
「ほなら兄さん、手伝うてくれんかの、」
「オイがか、」
どうやら、全国的な風潮のようである。ちなみに五十九年度岡山大学の学祭も、どういう理由でかおこなわれてはいないし、又、他の行われている大学にしても画一的なものが多く、その学祭は遜色たがわず独自性に乏しい。
当初、史邦はここだけの問題かと思っていた。
この時期、史邦は何だかんだと訳の分からないまゝ日をつないで、毎日グランドに出てはピストルばかり撃っていた。そのピストルの爆音に合わせて、ラガーシャツやサッカーシューズといった色とりどりのユニフォームがダッシュしてゆくのである。
史邦は走らない。今更走ってみてもしかたがないから、これだけで良かろうというのであるが、その実走って連中に勝るとは考えておらず、それが本音であったろう。勝てなければ、今はいないにしても、その内に当然ながら不平分子が出てくるものだ。そう思っていた。だから、日々ピストルばかり鳴らして遊んでいた。
キャンパスの裏の一段あがったところのグランドを使用するサークルは、かれら史邦の陸上部の外に軟式野球部とソフトボール部があり、軟式とソフトの二つのダイヤモンドがグランドの東半分を占めている。都合陸上部は残りの半分を使用することになる。つまり軟野がグランドの四分の一を占め、ソフトも同四分の一、陸上部は二分の一の面積を有している。他のクラブ員たちは、一回生ばかりのこの団体をうさんくさくも空いた場所にいるかぎり、まあいいだろう位に認めていた。グランドの西側手前、工学部の実習棟からあがったところに倉庫代わりに使われているプレハブの建物がある。
先程から史邦は足を投げ出してプレハブにもたれかかっていた。今日の分のピストルは撃ってしまった。既に用はないのである。連中が史邦の前を通過するたびに、座ったままニッと笑顔を向けるだけで、後はただぼんやりと空を見上げている。
先頭で連中を辛島がひっぱり、槙野が後から遅れそうになる部員とついてゆく。それぞれの味がでていていい光景だと頭の中で史邦はつぶやいた。彼らはグランド一杯に大きく旋回する。
何度目か、史邦の前を通過した時に辛島が群れからはぐれてやってきた。
やってくるなり史邦の傍らに腰をおろし、疲れたと言った。史邦は、そうか、と一言言っただけで後はまたにやにやしている。にやにやしているだけで何も言わないものだから辛島は場を失い、それじゃあ、と群れに帰ってゆく。その姿を目で追いながら、ふと目を転じると、工学部の実習棟の辺りから頭が二つ見え隠れしている。どうやら、気づかなかったが先程からそこに頭が二つあったようで、その頭が二つずっとこちらを窺っていたのであった。
「こっちへ来て一緒に見んか、」
と、史邦が声をかけると、ひとたび頭と頭がくっついて、やがてごそごそと這いあがってきた。
「おーよお来た、よう来た、こっちへ来いや、」
グランドに現れた二人はもじもじとしながらも、引きつけられるようにして史邦の傍らまでやって来た。
「立っとらんとここへ座れ、一緒に見ようぜ、」
二人の男は、ハァと言いながらも、それでもまだうさんくさく若干史邦との距離を置いて団子になった。
あの先頭を走っている黒い男が辛島という男で、あれで結構ハンマーを飛ばすんだ、とか、しんがりは槙野というて、あれでなかなか洒落た男だとか、二人を前に史邦は部員各員の説明を始めている。
「分ったかい、」
部員たちは走るのをやめ、ちょうど史邦達の見ている前で体操を始めた。
「はあ、」
としか言わない。
「そうか、ほなら一緒になってやっておいで、」
「えっ、」
「俺は消える、」
と、手に持っていたピストルを一丁渡すと、実習棟の方へぶらりと消えて行った。
そろそろ時刻である。
と、思った史邦ではあったが、実際には定刻をはるかにオーバーしていた。
「えーそこで、今日の会合の決定事項のひとつである主題(テーマ)についての話しじゃが、各員の意見を聞きたい、各自述べられよ、」
本実行委員長になった冨永が座った。
一人々々が順を追って発言する。
「お兄さん、何うしようったんじゃ、四時半ちゅうとったろうが、」
と、小声である。
「いやあ、すまんのお、遅れてしもうた、」
「そんなこたぁ分かっとる、」
それより、と冨永は遅れてやって来た史邦の為につい今しがたまでの会合の流れを大まかに説明した。
「福岡大は五百万ちゅうとるゾ、嘘かもしれんが、ここいらじゃあ隣の市大でさえ九十万じゃ、女子大が六十万ちゅう時にうちゃあ全部で三十万しかねぇ、これでどうせぇちゅんじゃ、こんなんじゃあ恥ずかしゅうて奴らと話もできるか、」
いうまでもなく、学祭の予算の額を言っているのである。
「冨永さん、」
と、一人が言った。各自が一通り終わったところで、どうも今日決定するにしては甚だ時期尚早ではないかと言う。要するに誰もが多分誰かが考えて来るだろう位にしか考えておらず、真剣味が伺えないのであった。
「何をいうとるんじゃお前ら、後一ヶ月しかないんじゃゾ、」
誰もやらない学祭の尻拭いをさせられる羽目になった人間が強引に集めた連中だけに当然といえば当然のなりゆきであったかもしれない。それにしても、学祭当日までに正確には一ヶ月を切ってしまうという時期まで事が興らないというのも、かなり異常な事態であるのだが。
学生が大学祭に積極的な参加を示さなくなったのは何もここだけの話しではなく、どうやらむしろ全国的な風潮であるらしかった。いや何も学祭に限ったことではなく、当世学生気質全般の問題のように思えてならない。学祭はあくまでその気質が端的に表される、ひとつの場にしか過ぎない。
結局その日の内には主題は決まらなかった。学祭のテーマこそ決まりはしなかったが、半ば暴力的に冨永は議事を進行させ、冨永の持ち前の気迫の前に皆は隊列を組まされる格好になっていった。
(これでいい)
と、史邦は思った。
冨永にはその能力がある。その能力はこういう急場に置かれた場合に発揮されるものである。なまじ理屈で事をおしてゆくと、かえってその理屈は成り立たない状態に陥ってしまうものである。
「広告取りもせねゃあならんけど、何をどうすりゃあえゝか分からんさっぱり分からん、あの馬鹿めが、」
あの馬鹿とは前年度実行委員のことであり冨永らが第七回実行委員であるから、ここの場合第六回までのメンバーのことをいっているのであり、特に誰という訳ではない。
前回までの実行委員は殆ど何も資料を残さなかった。パンフレット作成のスクラップでも残っていればと思い実行委員室をくまなく探した史邦と冨永ではあったが、出てきたものといえば不必要だと思われる量の第六回パンフレットの山だけであった。
「無駄なことをしよおる、」
実際、無駄といって好い程の量がほこりをかぶって出てきた。その場その場の無計画さが露呈している。
(まあ、しかし、彼らも誰もやらぬ学祭をおしつけられたのであろう)
だから、引き受けただけでもよしとせねばならぬのか。
広告取りは前年のパンフレットに掲載されている所をそのまゝ再度頼み込むことにして各店の割り振りを総員に当てた。
「俺はこの店とこの店を、」
と、冨永は各員に割り当てた量の数倍の店をまわるつもりであるらしい。独り占めした。
「その必要はない、」
とは史邦。
「委員長は黙ってこの場所に座っていれば良い、余計なことはせぬことじゃ、」
更に、冨永がまわるつもりでいた広告取りを、史邦は各員に割り当てた。
「契約がとれ次第、随時持ってこられよ、本日はこれまで、」
実行委員室には途中経過が一目で分かるようにと広告取り一覧の計画書が貼り出された。
「ところで、いったい俺達は何をやる、何をやればいいんだ、」
「大学回りをやる、とにかく人を集めることじゃ、」
事実、前年度までの様子では特にうちの大学には人が集まって来ない、人が集まらず、結局のところ寮の学生達ばかりが半ば強制的に参加させられているに過ぎず、見渡せど身内ばかりというのが実情であった。
人が集まらないのには、それなりの原因がある。この大学の学祭には企画がない。人間を一ケ所に集中さすに足る目玉的企画がまるでない。
「まづ、人を集めることを考えるべきじゃ、」
「どうやって、」
「それをこれから考えるんじゃぞ、二人で、」
「二人でねぇ、」
冨永は両の腕を組み考えてしまった。
「力んでも何も生まれて来んぞ、自然の流れにそうことじゃ、」
「自然のねぇ、」
「つまり、現状で出来ることを考える、ひとつのものが持っているものを最大限に増幅させてやることじゃ、思っている方向へ向かって、」
冨永は考えを巡らしている。
寮に戻り、史邦は冨永の部屋を訪ねた。
「何か生まれたかの、」
「それが問題じゃ、何も生まれん、別に力んでいる訳じゃあないがのさっぱり浮かばんのじゃ、」
「そうか、」
「そうなんじゃ、どうもこういうことは俺にゃあ向いてねぇように思う、」
「向き不向きがあるもんのお、いや失敬、」
「白状する、わしゃあ駄目じゃ、」
「そんならな、」
と、史邦は喋り始めた。別に以前から考えがあって、それを冨永に隠していた訳ではなく、一度喋り始めると次々に案が出て来るのである。そういう能力をこの男は持っている。
「……をすれば、」
と、史邦の頭中に漠然と浮かんで来たものが、彼の言葉を借りてどんどん純化され、殆ど最終的なものとして姿を持ち始めた。まるで、雰囲気から具体が産み落とされるがごとくの光景である。
冨永の部屋には既に二個の有機体は存在しておらず、その色彩は一色に塗り替えられていた。
「……それでの、」
聞く冨永は別世界の生物でも見るかのようにと書けば大袈裟かもしれないが、正体なく史邦の創造物を受け入れるだけで精一杯であった。
冨永が現実の世界に引き戻されたのは、史邦を探しにやってきた辛島の声を耳にしてからであった。
冨永は辛島が断りもなく部屋に入って来たことに、
「ナンカ!何ばしよっとかお前は、誰が入れちゅうた、ですぎるな、」
と、辛島の胸ぐらを掴み激怒した。
ことのついでに辛島を廊下に捨てた。
目が座っている。
(こりゃあいかん)
「今大事な話の最中でな、はよぅお帰り、」
と、史邦は廊下に言った。
「はぁ、」
と、立ち去ろうとした時、
「ちょっと待て、断りをしてゆけ、」
と、史邦は呼びとめた。
「お兄さんを何じゃ思うとるんじゃ、おめぇらが思うとるようなひとじゃねぇぞ、」
と、冨永。
「もう、いね、後でゆく、」
(そろそろ切りあげるか)
「それでな、こうなんじゃ…、」
と、冨永相手に何もなかったかのように話をつないだ。
「…まあ、そういうこっちゃ、そういうことでやってみよう、」
終止符を置いた。
辛島の用件というのは陸上部の問題であった。聞くところによれば何でも入部希望者がいるにはいるが、その入部希望者を部員達が拒んでいるということである。何故拒むのか定かではなく要領を得ない。
槙野を呼んで来た辛島は再び説明し始めた。
入部希望者とは昼間史邦からピストルを渡された二名であること、その両名がどうも部員達と肌が合いそうにないこと等を話す。
この時期までには、部員達は既に中国四国学生陸上競技連盟岡山大会を参加はしていないが経験済みであり、気心は知れる様になっていた。
「そうかそうか、入部したい言うたか、」
「だから問題なんです、中村さんがピストル渡すからこうなるんですよ、」
「問題にも何もなりゃあせんがな、入りたい言うとるもんを入れん道理はありゃあせまぁが、」
むしろ問題にすべきは受け入れ側にあるとでも言いたかったのかどうか、それはさておき史邦は続ける。
「自分らに肌が合いそうもないかどうかは知らぬが、それをまとめてゆくのがお前らじゃろが、しっかりせぇ、それで入部するな言うたんか、」
「言うてません、」
と、槙野が言う。
「ただ、あっさりと入れたもんかどうか、」
「入れちゃれ、入れちゃれ、仲良うやれ、」
あっさりと入れたものかどうか迷った槙野は入部を拒否するに足る理由もこれといってないものだから、入ってもすぐに辞められたのでは困るから、当分の間部員と一緒に練習をして、それでもやってゆける自信が着いた時に入部されたい、と、彼ら両人に告げたというのである。
(問題などありゃあせんがな)
連載小説「デッサン いろはにほへど」をまとめて読む
(1)門出の花
(2)馬関へ
(3)陸援隊
(4)桜の木
(5)憂
(6)惨風
(7)思案
(8)思案その二
(9)物情騒然
(10)刺客
あとがき

準備中