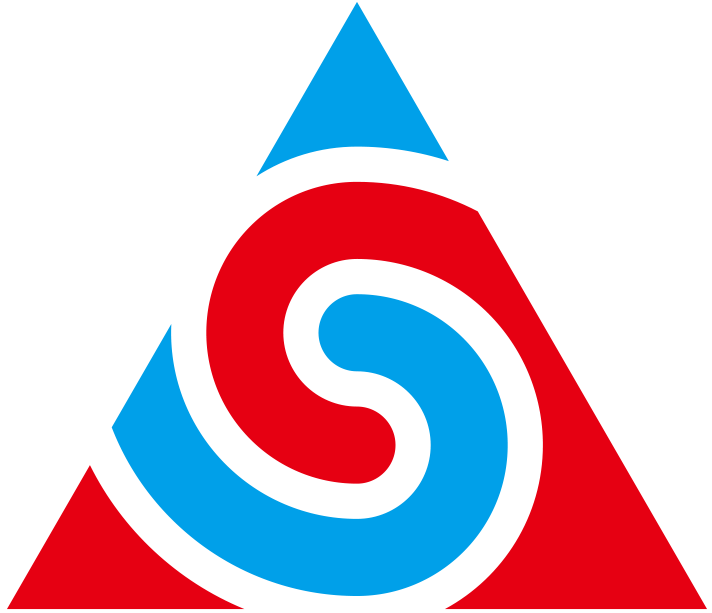 連載記事
連載記事2025/02/16
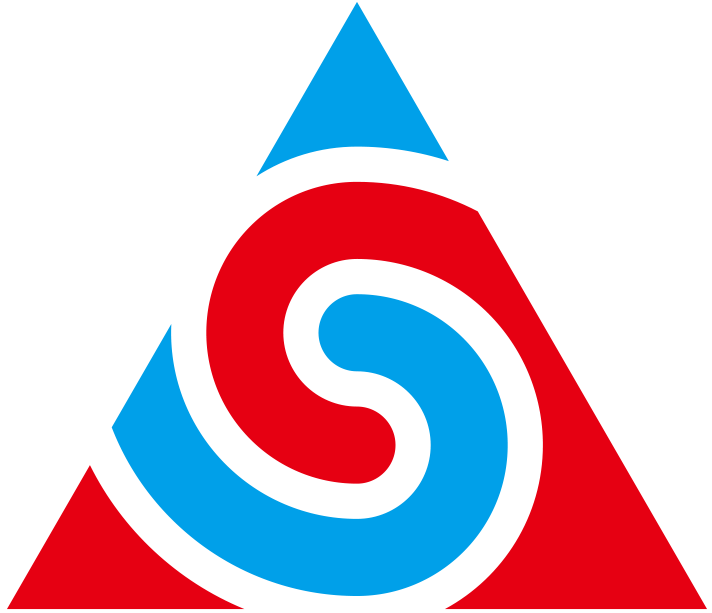 歯を磨く様に演じる
言葉ついての講師依頼がありまして…
歯を磨く様に演じる
言葉ついての講師依頼がありまして…


劇団としてではなく、一人で仕事をする様になって様々な講師のご依頼を頂く。例えば高齢者向けの発声、新学期になって新しい保護者同士の仲を深める為のコミュニケーション、子供達のコミュニケーション、演劇の基礎、若者の就職を助ける為の講座や面接、言葉で特に敬語について、言葉のアクセント。他にもいろいろ。何でも屋である。
その中で教える側であり、日頃自分でも気をつけたいと思っているのが敬語を含めた言葉である。
ある所で行った敬語の講座で感じたことだが、年齢も自分より上の参加者が多く、何十年と社会でお仕事をされているので、特に初対面ではそれ程会話を交わしていない事もあって問題がある様には思えない。
だが、QアンドA方式で問題を解いていってみると、わかっているけど、日常使っていないであろう言葉があったり、言われた事に同意、納得する言葉「なるほど」「たしかに」など上の者に対して敬語に言い換えるべきなのだがあまりにも日常「なるほど」「たしかに」と使いがちなせいもあって、口から出るには難しい言葉があるようだ。私もわからなくもない。目上の人には「了解です」ではなく「承知しました」など自分が使い慣れてしまえば逆に、敬語を使わないのは違和感が生じ気持ち悪くなるのだが…。
まあ、一つずつ自覚したらメモでもしておいて口慣らしをする様に使っていくのが良いのではないかと思う。そうするとそのうちに自分の言葉になる。
ある時、とても丁寧な言葉でメッセージを頂いた事がある。私はその方に対してフラットな立場で対応していたのだが、
「〇〇を教えてください」を、
「〇〇をご教示ください」
と敬語が使ってあり、(なかなか頂いたメールでこの言葉を見たことが無く)少しキュッと身が引き締まる思いがしたのを思いだした。
それとよく言われるのが「来れる」「食べれる」などの「ら抜き言葉」。これを不快に思わない方もいる様で、個人の会話はともかくとして、公の場で使うのは避けると良いのかもしれない。ちなみに自分が教える立場の場合は、「『ら抜き言葉』は使わないように努力しましょう」と伝える。
この「ら抜き言葉」に関してとても抵抗感を感じている方がいらっしゃるのだなと第1回鶴屋南北戯曲賞受賞の永井愛さんの戯曲「ら抜きの殺意」を読んで思っていた。
永井さんのあとがきには「『ら抜き言葉』は一時はやって消えてゆくようなものとは違う。多くの人がごく自然に受け入れつつある言い回しの変化である。私は、私の大前提であった東京弁の根幹が変えられてゆく過程に立ち会っているのだ。それは、私自身をも変えられてしまうような戸惑いを引き起こす。私とは、私の発する言語だと言ってもいいだろうから。」(永井愛『ら抜きの殺意』より)と書かれている。
個人的にはら抜きのサウンドが嫌いなので、不意に出てしまった時などは、言い直したい衝動に駆られる。
素敵な方にお会いする事もよくあり、何が素敵かと言うとその方が発している言葉が素敵で、そのサウンドだったり使われている言葉だったりスピードだったりする。ある知人の男性に、
「素敵な女性ってどんな人?」
と聞いた時も、
「素敵な言葉を使っている人」
と言っていた。そこを目指しているのだが、自分のトークを聞いてみると、妹の嫌いだった喋り方にそっくりで嫌になる。
それはさておき荒木昭夫先生の脚本演出の作品をしている時どうしても稽古でその台詞が出てこず稽古を止めるわけにもいかないので、意味は同じ様な似た言葉で台詞を言っていた事があった。その時荒木先生は私に、
「その言葉を使う女の子なんですよ」
と。人格や性格が反映すると言うわけなんですよね言葉は。

準備中